日本酒のソムリエといわれる「唎酒師(ききさけし)」が、飲食店をはじめ、様々な業界で活躍しています。「唎酒師」は、日本酒を造る酒蔵と消費者の間に立ち、季節やシチュエーションなどを考慮して、日本酒の美味しい飲み方を提案するプロフェショナルです。
資格認定をする「日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会」(SSI)によると、これまでの合格者数は3万3267人(2018年2月現在)。酒販店や飲食店で働く人たちだけでなく、日本酒が好きな一般消費者の取得も近年増えているそうです。
「唎酒師」の誕生から約27年、誕生に至った経緯から今後の活動について、同会専務理事の日置晴之さんに話をうかがいました。
発足の経緯は、自国のお酒を語れなかった苦い思い出
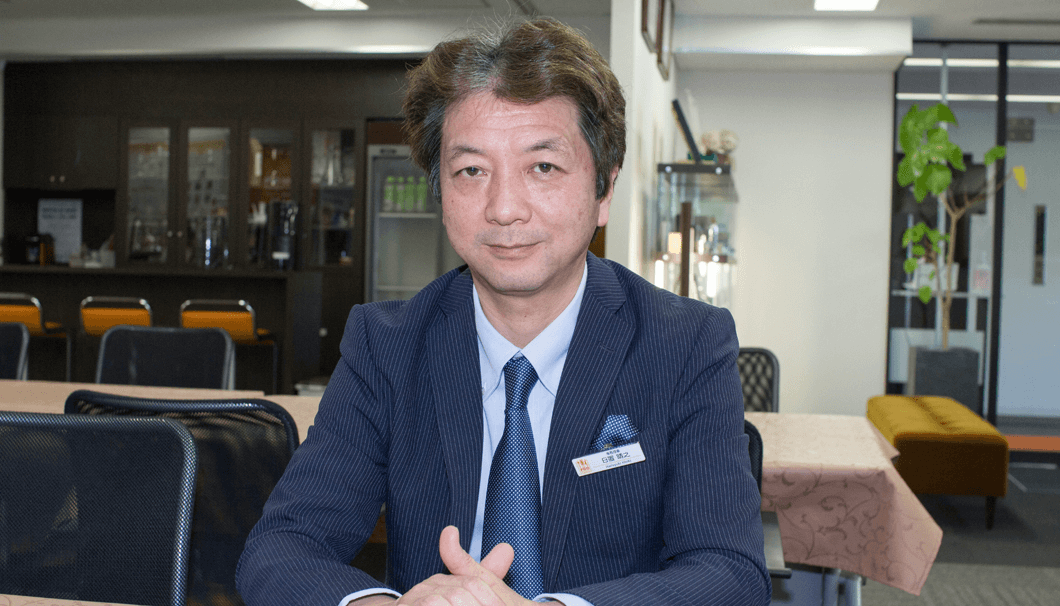
SSI専務理事の日置晴之さん
SSIが設立されたのは1991年。当時の日本は、フランスやドイツなどの輸入ワインの需要が伸び、ソムリエがどんどん増えていいました。「唎酒師が誕生した背景は、自分の国のお酒をちゃんと語れなかったという苦い思い出からなんですよ」と日置さんは語ります。
そのころ、日本のソムリエのレベルは、海外の様々なコンクールでも活躍するまでに向上していました。日本から選抜されたソムリエが、自分の国のお酒である「日本酒」について現地の人に聞かれることもよくあったそうです。しかし、ソムリエたちは「日本酒」のことをあまりよく知らなかったため、きちんと受け答えができなかったのだとか。日置さんは「外ばかり見ていましたが、自分の国のお酒を何も知らなかった」と、当時を振り返ります。そこで、日本酒をきちんと学んだ上で、国内外に広く伝えていく必要があるとして、SSIの活動がスタートしました。
日本酒の魅力を伝える「唎酒師」の必要性

発足当時、SSIの正式名称は「日本酒サービス研究会」でした。現在の「日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会」という長い名称になった理由は、蔵元が主導していた、消費者への日本酒啓発を目的に行われる「日本酒アドバイザー友の会」と「酒匠研究会」が、同会の活動に深く共感し、1994年に合併したためです。
画期的だったのは、それまで、蔵元が行うテイスティング(きき酒)は「出荷する日本酒に欠点がないかを見つけるマイナス評価」が主体だったのに対し、唎酒師が行うテイスティングは「出荷されたお酒の魅力や個性を見つけるプラス評価」だった点でした。
「日本酒の品質が良くない時代は、確かにありました」という日置さんの言葉どおり、米不足の影響で、糖類や醸造アルコールで増量した日本酒が主流になった時代や、香味ではなく、そのお酒からどれだけ税金を徴収できるかでランクが決定されるような級別制度の時代もありました。この級別制度は、SSIが設立された翌年に廃止されましたが、新たに誕生した特定名称の制度も、消費者にはわかりにくいものでした。そんな時代だったからこそ「正しい知識と楽しみ方を伝える唎酒師の役割は大きかったのではないでしょうか」と日置さんは語ります。
必要な能力は、当時も現在も変わらない

発足当時と現在の試験内容の変化について尋ねると、「一部変化しているものの、試験の内容は変わっていない」と語る日置さん。日本酒の基礎知識やサービスに関する知識をもとにテイスティングを行い、日本酒の個性・魅力をしっかりと把握したうえで、消費者にベストな提案をする能力があるかどうかを試験で測っているのだそう。
また、日置さんは「資格の取得がゴールではなく、継続して勉強することが大切」と話します。実際にSSIでは、唎酒師の取得者を対象に、伝えることに特化したインストラクター資格「日本酒学講師」(のべ合格者423名:2018年3月末現在)や、より専門性の高いテイスティング能力を有する「酒匠」(のべ合格者377名:2018年3月末現在)などの資格認定も実施しています。
日本酒の未来を握る「唎酒師」

国税庁の統計によると、日本酒の消費量は1970年代をピークに、現在、およそ3分の1まで減少したと言われています。一方、海外輸出に目を向ければ、ここ10年で、数量ベースでは2倍、金額ベースでは3倍の伸びをみせています。この状況のなか、日置さんは「日本酒の輸出が増加していますが、海外には、日本酒の正しい知識をもって、その魅力を伝える人が足りていません。我々も、台湾や香港などのアジア圏をはじめとする海外のスクールと連携し、日本酒の楽しさと正しい情報を配信していきたいと思います」と語りました。
このような思いがすでに実を結び始め、「唎酒師」の海外版ともいえる「国際唎酒師」は、すでに2000名を超え(のべ合格者2095名:2018年3月末現在)、各国で日本酒の魅力を伝えています。

国内外問わず、日本酒が正しく継承されていくためには、日本酒のプロフェッショナルである「唎酒師」や「国際唎酒師」の存在が必要であること。そして「唎酒師」や「国際唎酒師」の活躍が、まさに日本酒の未来を握っていることを強く感じました。
(文/乃木 章)





